
「AIがあれば誰でもデザインできる」は本当か?ー生成AI時代のデザイン思考
2025年11月7日、京都で開催された「生成AI時代のデザインを再発見する」ワークショップ。参加者24名のほぼ全員が満足度5点満点をつけた、このイベントで何が起きたのか。
「デザインって見た目を整えることでしょ?」
「AIがあれば誰でもデザインできるのでは?」
そんな誤解を抱えていた参加者たちが、4時間半のワークショップを経て、まったく違う景色を見ることになりました。
開催概要
- 日時: 2025年11月7日(金)14:00-18:30
- 会場: ストライク 京都イノベーションオフィス/Hive Kyoto
- 参加者: 24名(対面10名、オンライン14名)
- 講師: 塩月慶子氏(株式会社ライトライト CDO)、岡田拓也氏(同社PM)
- 形式: ワークショップ + YouTube Live配信
全5回シリーズ「Hackathon Meetup」の第4回目。前回までの技術習得から一歩進んで、「何を作るべきか」を考えるデザイン思考にフォーカス。事業承継プラットフォーム「relay」を運営する株式会社ライトライトの実務家による、実践に基づいた講義とワークショップを開催しました。

講師紹介
今回の講師を務めたのは、事業承継プラットフォーム「relay」を運営する株式会社ライトライトから2名のプロフェッショナル。
塩月慶子氏(CDO)
株式会社ライトライトのChief Design Officerとして、デザイン戦略全体を統括。携帯電話のプロダクトデザイナーとしてSHARPに勤務後、地域メディア制作、CAMPFIREでのクラウドファンディング支援、プロダクト開発などを経験。2023年からは株式会社ライトライトにて、プロダクトによる新しい事業承継のあり方を模索。2024年グッドデザイン賞を受賞。

岡田拓也氏(PM):
同社でプロダクトマネージャーとして、ユーザーニーズと技術実装の橋渡し役を担う。多数の地域プロジェクトやメディア運営、サービス開発を経験。2015年より継続的に様々な場で独自のワークショップを実施。

内容ダイジェスト
「デザイン=見た目」という常識が覆された瞬間
ワークショップが始まって最初に衝撃を受けたのは、塩月氏のこの一言でした。
「デザインとは、ニーズと理念の交差点を探す行為です」
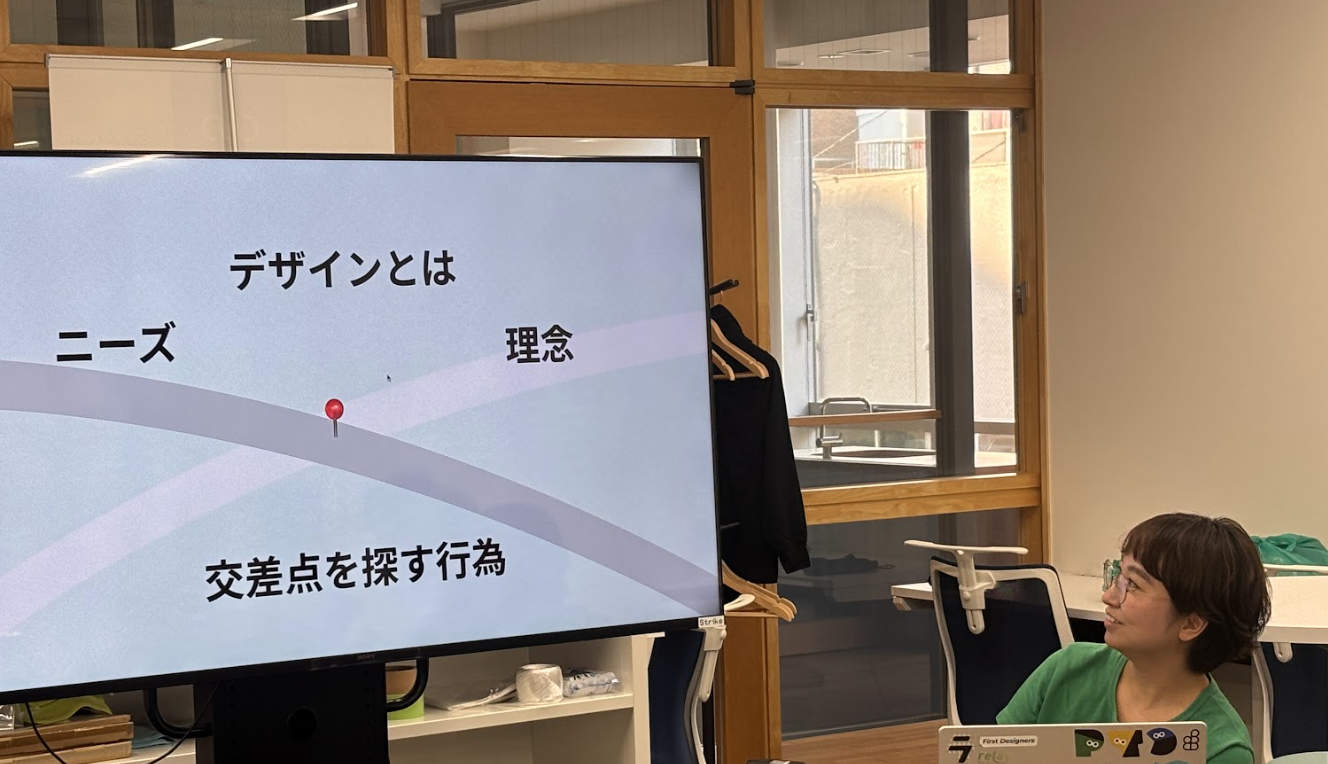
正直、最初は「?」でした。デザインって、色を決めたり、レイアウトを整えたりすることじゃないの? そう思っていた参加者は僕だけではなかったはずです。
でも、塩月氏がrelayでの実例を話し始めた時、腑に落ちました。
「カードデザインを改善する時、既存のセオリー通りに作っても上手くいかなかったんです。大切だったのは、ユーザーが本当に求めているものと、私たちが実現したい世界観が重なる部分を見つけることでした」
つまり、デザインの本質は「問題を見つけること」だったんです。見た目を整えるのは、その後の話。
AIに熱量は宿らない
続く岡田氏のセッションでは、さらに核心を突かれました。
「AIは表現の幅を広げてくれます。でも、"何を作るか"を決めるのは人間です」
ここで印象的だったのは、「欲しいものを想像できる人」こそがデザイナーだという話。

AIに指示を出せる人は、すでに頭の中に「こうあるべき姿」が見えている。その想像力は、自分自身の経験からしか生まれない——この言葉が、妙にリアルに響きました。
確かに、AIに「かっこいいデザインにして」と言っても、何も生まれない。「誰のどんな課題を解決するために、どういう体験を提供したいのか」が明確じゃないと、AIも動けないんです。
紙とペンで「交差点」を探す
後半のワークショップでは、実際に手を動かしました。紙とペン、それだけ。
グループでディスカッションしながら、「誰のどんな瞬間を変えたいのか」を考え、核となる体験を設計していきます。
アナログなワークだからこそ、じっくり考えられた。AIに頼らず、自分の頭で「交差点」を探す体験は、思った以上に手応えがありました。
一番の気づき:自分の経験が武器になる
今回のワークショップで最も印象に残ったのは、「自分の経験が武器になる」という事実です。
AIが発達すればするほど、「誰でも同じものが作れる」ように感じていました。でも、違ったんです。
何を作るか、誰のために作るか、どんな体験を提供したいか——これを決められるのは、経験を持った人間だけ。AIはその実現を助けてくれるツールに過ぎない。
4時間半のワークショップを終えて、デザインに対する見方が完全に変わりました。

アンケート結果
イベント終了後、対面参加者全員がアンケートに回答してくれました。
満足度・理解度
- 満足度: 4.9/5.0(90%が5点、10%が4点)
- 理解度: 4.6/5.0
- ハッカソン参加意欲向上: 60%
- 次回参加意向: 70%が「ぜひ参加したい」「都合が合えば参加したい」
参加者の声
実務に基づいた具体的な体験談が、多くの参加者の心に響いたことが分かります。
今回のイベントに参加して学んだことは、『人間の経験値』と『内的モデル』が重要になることです。AIに生成させるだけで表現はしてくれるけれども、自分の世界観や経験値がなければ最適な回答が得られなかったり、自分の表現したいものを出力することができないと考えています」(大学院生)
「本日は参加してよかったと思いました。刺さる言葉が多く、今後の業務の参考にしていきたいと思います」(ストライク社員)
「自分の知らない思考法や体験が武器になると気づけました」
「デザイン未経験のエンジニアでしたが、デザインが身近になりました」
次回予告
今回のイベントは、全5回シリーズ「Hackathon Meetup」の第4回目でした。
- ハッカソン体験談(済):モチベーション向上
- API開発(済):バックエンド基礎
- React UI開発(済):フロントエンド実装
- デザイン思考(済)← 今回
- プレゼン術(12月予定)← 次回
Hackathon Meetup #5:プレゼン術・総仕上げ
シリーズ最終回となる次回は、ハッカソンの成否を左右する「伝える力」を磨きます。
どんなに優れたプロダクトを作っても、その価値が伝わらなければ評価されません。最終回では:
- ハッカソン発表の構成術
- デモの効果的な見せ方
- 限られた時間での価値の伝え方
- Q&A対応のコツ
を実践的に学びます。
こんな方におすすめ:
- 作ったものを魅力的に伝えたい
- プレゼンに自信がない
- ハッカソンでの発表を成功させたい
- 審査員に刺さる伝え方を学びたい
詳細は後日connpassにて公開予定です。